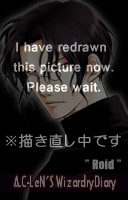128.臭い
「ただいま」夜更け近くになって、ドアの音に続いて聞こえたブルーベルの声に、ヒメマルはほっとした。
今日はこの部屋には帰ってきてくれないかも知れない、と思っていたからだ。
「おかえり、大荷物だね」
「…うん」
ブルーベルはパンパンになっているザックを床に降ろした。
ゴトン、とガラス製の重い音がする。
「夜のパーティに、ロイドって男がいるんだ。サムライなんだけど」
ブルーベルは汚れたローブを脱ぎながら、抑揚のない声で話し始めた。
「うん」
「ムラマサ使ってるんだけど、イチジョウみたいにマジックアイテムで抑えたりしてなくて、平然と振り回してるんだ」
「すごいね、精神力が強いのかな」
「でも今日は調子悪かったみたいでさ、しょっちゅう首かしげてた。そのたびに俺の方見るんだよな」
「うん」
「帰り際になって、言われたよ」
「なんて?」
「お前からキャドの臭いがするって」
「え?」
「ロイドは人狼なんだってさ、それもハーフとかじゃなくて、生粋の」
「そうなんだ」
「で、彼にはキャドの臭いが邪魔らしいんだよ。ナワバリ意識だとか、そういう本能的なものがあるんだって。それのせいで、キャドとロイドってかなり仲悪いらしい」
「なるほど~」
「だからキャドの臭いがするだけで、全然集中できないんだって」
「そっか。鼻の利く種族だと、そういうこともあるんだろうね」
「それで、言われたんだけど」
ベルはヒメマルをじっと見つめた。
「恋人がいるなら、そいつの臭いをつけてこいって」
「へっ?」
「キャドが恋人なのかって訊かれたから、しばらく一緒にいたけど違う、つきあってる男は他にいるって言ったんだよ。そしたらそう言われた」
「、、で、も、臭いって言われても、、どう?」
「…」
ブルーベルは少し頬を染めて、唇を尖らせた。
「手っ取り早いのは、マーキングだって」
「…それって…つまり…」
ヒメマルの頭に、イヌ科の動物が縄張りを主張する時のマーキングが思い浮かぶ。
「寝る気になれなくたって、それくらいなら出来るだろ?」
「え?えええ!?」
ヒメマルは、大いにうろたえた。
「それって、ある意味、エッチするより、あの…」
「なんだよ!!そんじゃロイドに臭いつけてもらうぞ!!ほんとはそれが一番なんだからな!」
ブルーベルは脱いだローブを床に叩きつけた。
「だっだめ、だめ、それは嫌だよ」
「じゃ、やってくれるよな」
「ほかに手はないの~!?」
「ないって」
「ほかのパーティに入るっていうのは、どう?」
「みんな大人でベテランで、すごくいいパーティなんだよ!臭いなんとかしなきゃ明日からパーティに入れてもらえないんだ、ヒメマルが協力してくれたらそれで済むんだよ、それくらいしてくれてもいいじゃないか!!」
「…」
ブルーベルにまくしたてられて、ヒメマルは唾を飲み込んだ。
「ベルは、そういうこと、されてもいいの?」
「いいよ」
「そんな、あっさり…」
「うだうだ言ってないで、とにかくビール飲んで腹いっぱいにして。買ってきたから」
「…え~」
ヒメマルは両手で顔を覆った。
「思い切り悪いなぁ、男だろ?」
言いながら、ブルーベルはザックから大瓶のビールを5本取り出した。
「こういうのに、男らしさは関係ないよ~」
「ほら、飲んで」
テーブルの上に、どん、どん、と並べていく。
「…コップは?」
「ない。ヒメマル弱くないだろ、ラッパでいいじゃん」
「はぁあぁ…」
ヒメマルは、大きな溜息をつきながらビールの栓を抜いた。