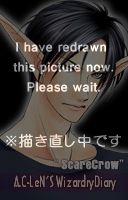287.スケア
値札の金額は、今持っている貯金の約八割だ。とてもではないが手がでない。これを買うなら、装備を整えるか旅費を溜め込んだ方がいい。-やっぱこういうのって贅沢品なんだよなあ…
トキオが考え込んでいると、
「こういうのが似合うんなら、エルフか?派手なヒューマンの女かな?自分でつけるわけじゃないだろ?」
エルフの青年が言った。
「いや、エルフのおと」
言いかけて、トキオは小声になった。
「男…」
「あぁ、エルフは男でも似合うよな。俺みたいな奴にゃ似合わないけど」
青年は気さくに言った。プレゼントの相手が男だということは、特に気にならないらしい。
「そうか?」
トキオは青年を眺めた。
「服装次第じゃねえかなあ?こういうのとか、このへんなんか…銀はかなり似合いそうだけどなぁ」
手に取るわけにはいかないので、トキオはいくつかの装飾品を指差して言った。
「そぉかあ?」
まんざらでもないようだ。青年は笑って頭を掻いた。
「自分用じゃないんなら、あんたもプレゼントか?」
トキオが訊くと、青年は首を振った。
「俺はドワーフの細工モンが好きなんで、見てるだけだ。こんな高級品買う金ないよ」
あっけらかんとそんなことを言う。トキオは思わずカウンターのドワーフに目をやったが、こちらのことなど気にしていないようだ。
「このレベルの細工は、エルフや人間にゃ真似出来ないよな。やっぱドワーフ製は格が違うやねえ」
青年は近くにある腕輪をじっと見た。お世辞を言っているような表情ではない。
その横顔をやはり知っているような気がして、
「あのさ、どっかで会ったことあったっけな?」
トキオは訊いてみた。
「あんたと?」
青年はトキオをじっと見てから、確信のない声で言った。
「…宿で、ドアが開かないって騒いでたか?」
「あぁ!!」
静かな店内で大きな声を出してしまって、トキオは自分の口を塞いだ。
「そうか、あん時鍵開けてくれた…」
クロックハンドの部屋が開かなかった時に、上半身裸で飛び出してきた隣の部屋のエルフだ。
あの時は寝不足で怒っていたからか、もっと人相が悪かった。
「礼も言えなかったけど、ほんと助かった。ありがとう」
「いやあ、ただ安眠したかっただけだから、礼なんてよ」
青年は明るく笑って、手を差し出した。
「俺はスケア」
「トキオだ」
トキオは青年の手をしっかりと握った。
「鍵開ける魔法なんて初めて見たけど、どっか遠いとこから来たのか?」
「そりゃもう遠い遠い」
「もうすぐ看板だぞ」
奥からドワーフの声がした。
「っと、良かったらどっかでちょっと飲むか?」
「うん」
スケアの誘いに、トキオは頷いた。このエルフには好感を持ったし、遠い国の話にも興味がある。
*
クロックハンドとブルーベルは、夜のパーティ解散後、酒場でひと息ついていた。ミカヅキが見当たらず、他に前衛の知人もいなかったので、それならばと、体力の余っていたクロックハンドが入ったのだ。
他のメンバーは、スリィピー、アンバー、ビオラ、ヘスで、ブルーベルの顔見知りばかりだったが、クロックハンドはすぐに溶け込んで、問題なく短めの探索を終えた。
「まだカドルト使われへんのかあ。ベルちゃん、めっちゃ潜ってるんとちゃうん?大変やなあ」
「僧侶からビショップになれば良かったよ」
ブルーベルが口を尖らせる。
「カドルト覚えたいんって、ヒメちゃんの為だけにやんなあ?」
「うん。普通に蘇生するなら寺院の方がいいし。」
「愛やねえ~」
「うーん…、うん。そうかな」
ブルーベルはカクテルに唇をつけた。
「ベルちゃんがここまでしてくれとんのに、ヒメちゃん、なんであんな自信なさそうなんやろ」
「なんか言ってた?」
「ふられるかも、ふられるかもって、そんなんばっかり言うとったよ」
「何言ってんだろ。馬鹿だなー」
ブルーベルはカクテルに沈んでいたチェリーを摘み上げた。
「ふるつもりないんや?」
「ないよ。ヒメ好きだもん」
「それヒメちゃんに言うてあげてえな」
「言ってるんだけどな。仕方ないな、あいつ」
ブルーベルはチェリーをぺろりと舐めて、空いた小皿に置いた。