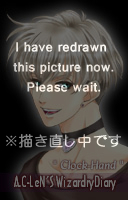146.気分転換
「そや、そんくらいの長さで、前は分け目つくらんと。後ろは刈りあげてんか。あとはそやなあ、ゆるーにパーマでもあててもらおかな」そう注文した後、店員が「この感じかな」と差し出したカタログのイラストを見て頷いてから、クロックハンドは目を瞑った。
最近、2人のことばかり考えている。
今朝方、どちらを取るのかイチジョウに軽く訊かれて、
「どっちも、っちゅうのはナシかなあ」
と答えたのは、ある意味では本心だ。
どちらかを取れと言われても、タイプが違いすぎるせいで比べようがない。
安定も欲しいし、刺激も欲しい。
このままの状態でいられたら一番いいのだろうが、2人がそれを許すとは思えないし、何より自分の居心地が悪い。
何事もはっきりさせないと気がすまないクロックハンドは、本来二股をかけられる性格ではないのだ。
―決められへんのは、どっちも好きやから…だけやないな。損得勘定してるからや。そういうんって、恋愛やないんと違うかなぁ…
こんなことを言うと贅沢だと言われるのはわかっているのだが、真剣な片想いをしているトキオが少し羨ましい。
悩むこと自体が嫌いなので、いっそのことどちらからも離れた方がいいのではないかと思うことすらある。
気分転換に髪を切りに来たのだが、この調子ではあまり効果はなさそうだ。
*
軽くなった頭に、くしゃくしゃと手ぐしを通しながら、クロックハンドは美容院を出た。大通りの服屋でこの髪に似合う服を探すつもりだが、その前に―
「お前、それでも忍者か」
クロックハンドは、美容院の大きな立て看板の下から見えている皮のブーツの脛を蹴り飛ばした。
看板の向こうから出てきたミカヅキを見て、クロックハンドは縦筋が出来るほど眉を寄せた。
「ギラギラしすぎやねん。俺はここにいますっちゅう気配が出まくっとるやないか」
ミカヅキは頬を僅かに染めて俯いている。
「尾けてきてどないすんのや。お前が後ろにおったかて、デートもするし泊まりにも行くぞ」
「…、」
ミカヅキは唇を噛んで、今にも泣きそうな顔をしている。
「こっぱずかしいから、泣くんやったら部屋帰って泣けや」
昨晩冗談で、
「どっちか選ぶん面倒やし、ダブルは恋人、お前は犬っちゅうのはどうや」
と言ったら、号泣されてしまったのだ。
あの勢いで泣かれてはたまらない。
「まあええわ。お前も服屋ついて来いや、新しい服買うねん」
ミカヅキは、ぱぁっと明るくなった顔をあげてクロックハンドに並んで歩きはじめた。
「ついでに、店のねえちゃんにコーディネートの基本教えてもらえ」
「うん。…あの」
「なんや」
「、髪。似合ってる」
「お前、どんな頭にしても似合ってるっちゅうやないか」
「…うん」
「まあ、しゃあないか。お前は俺に呪われてるようなもんやからなあ」
「の …」
ミカヅキは両掌を何度も振って否定した。
「呪いは、嬉しくない けど、 俺は、嬉しいから」
「嬉しいて思うのも効果のうちやろ」
「…この、」
ミカヅキは両手の指を組み合わせて、目を伏せた。言葉をまとめているらしい。
「この、俺の、状態が、何かの影響 に、よるものでも、好きなのは、同じだから」
「わかるようなわからんようなこと言うとるな」
「、恋愛感情は、多くの場合、…何らかの 影響による、個人の思い込み、だと思う」
「ああ、せやから自分のもれっきとした恋やて言いたいんか」
ミカヅキは真剣な顔で頷いた。
「それもそうかも知れんな」
店に着いた2人は、開け放しの入り口から店内へと進んだ。
「おーう、スッキリしたじゃねえか」
クロックハンドは、冒険者用の軽装を扱っているコーナーへ向う途中で、声をかけられた。
低いポールにかけられて並んでいる服の列の向こう側から、ダブルが顔を出している。
「そうやろ、やっぱりカリアゲてん」
クロックハンドは笑顔を返しながら、横目でミカヅキを見上げた。
案の定、親の敵でも見つけたような顔をしている。
「おかしなことすんなや」
小声で言うと、ミカヅキは何かを抑えるようにゆっくりと頷いた。
露骨に敵意を剥き出しにされて、ダブルは困ったように笑っている。
「そんな顔すんなよ、まだチューしかしてねえんだから」